
|
環境と公共性の社会学
|
この講義では、〈環境〉を〈誰が〉どう守るべきなのか、ということを中心に、次の点について考えます
(1)自然環境を守ろう、というけれど、「自然」とはそもそもどういういうものか? 人間の手がまったく入っていないもののことなのか?
(2)人間と自然の関係はどういうものなのか。地域の住民は、地域の環境に対し、歴史的にどうかかわってきたか、今後どうかかわるべきか。
(3)環境は誰が守るべきなのか。誰と誰がどういう関係のもとでどう環境にかかわるべきなのか。
(4)環境をめぐって、市民・住民が自ら決めて実行していく社会的しくみはどうすればできるか。
|
教員:
宮内 泰介(北海道大学大学院文学研究科) |
開講年:2006
|
タグ:
japanese, 学部でさがす, 心理/社会学, 文学/思想/言語, 文学部 |
講義投稿日:2017年8月9日 |

|
|
【概要】
臨床教育学を、教育と臨床心理学、教育と精神医学の接点領域から生まれる新しい思考と実践に資する領域と想定している。授業では出来るだけ現代の病理に沿りライフサイクル的視点から、精神医学全般の病理の概観を学ぶことを目標にする。
【スケジュール】
1.精神医学の歴史と関連領域
2.面接方法
3.診断学総論
4.乳幼児の精神発達と精神障害
5.小児の精神発達と精神障害
6.思春期・青年期の心性
7.成人の精神発達と精神障害
8.初老期・老年期の精神発達と精神障害
9.治療学
10.その他
|
教員:
田中 康雄(北海道大学大学院教育学研究科) |
開講年:2006
|
タグ:
japanese, 学部でさがす, 心理/社会学, 教育/学習, 教育学部 |
講義投稿日:2017年8月9日 |

|
|
【概要】
「環境マネジメントシステム」という考え方とは一体何なのだろうか。どのような背景の下にこのような考え方が生まれ、社会の中で広く共有されるに至っているのだろうか。環境マネジメントシステムという考え方を制度として具体化したものの一つが、国際標準化機構(ISO)が策定した国際規格ISO14001といえる。具体的な制度であるISO14001の、制度としての解説は世に溢れているが、その基となった考え方に関して言及がなされることは、殆どといっていいほどない。
本講義では、この環境マネジメントシステムという考え方に着目し、これが社会の中でどのように生まれ、広がり、そしてISO14001という国際規格になったのかを概説する。その上で、このような考え方が、これからの社会の中でどのような意味を持ち、また、どのような役割を果たしていくかを展望する。
【スケジュール】
1.問題提起(環境マネジメントシステムをどう捉えるか)
2.環境主義の台頭
3.環境監査の導入
4.地球環境問題の登場
5.地球サミットでの議論
6.ISO14001の策定へ
7.ISO内部での議論
8.ISO14001が持つ意味
9.普遍的な問題への対応
|
教員:
倉田 健児(公共政策大学院) |
開講年:2006
|
タグ:
japanese, 全学教育科目, 学部でさがす, 理学/自然科学, 理学部 |
講義投稿日:2017年8月9日 |

|
|
1.現代社会を考えるときの基礎的な概念を明らかにする。
2.社会科学における「理論」と「歴史」の意味,その相互関係を把握する。
3.現代社会科学が直面する問題群を提示する。
4.哲学,歴史学,心理学,数学,物理学,生物学などと社会科学の関わりを理解する。
|
教員:
佐々木 隆生(公共政策大学院) |
開講年:2006
|
タグ:
japanese, ビジネス/経済, 全学教育科目, 学部でさがす, 心理/社会学, 経済学部 |
講義投稿日:2017年8月9日 |

|
|
グラフ理論は自然科学のみならず、工学あるいは社会科学上の問題における要素間の関係を点と辺で表すことにより問題の見通しを立てやすくし、与えられえた問題の難しさを、 その解が存在するか、存在したら、どの程度効率の良いアルゴリズムが構成できるかという観点から解析・評価するための道具である。さらに個々のグラフの性質を巧妙に使ったアルゴリズムが開発され、実際に様々な場面に適用されている。
この講義ではグラフ理論の基礎的な概念/適用方法を定理とその証明のみに終始することなく、できるだけ豊富な具体的例題を通して説明することによって直観的に理解し、各自に演習問題を解いてもらうことにより、その理解を深めることを目的とする。
|
教員:
井上 純一(北海道大学大学院情報科学研究科) |
開講年:2005
|
タグ:
japanese, 学部でさがす, 工学/情報, 工学部 |
講義投稿日:2017年8月9日 |

|
|
情報理論は、情報の量を定義することから始まり、それを元にした理論を展開する。ここで学ぶ事柄、特に、エントロピーや相互情報量は、現在の通信技術の根幹を成すのみならず、パターン認識や、人工知能、あるいは統計物理、遺伝情報学などの多くの異なる分野において共有される重要な概念である。本講義ではこの理論の基礎を直感的に理解することに重点を置く。
|
教員:
井上 純一(北海道大学大学院情報科学研究科) |
開講年:2005
|
タグ:
japanese, 学部でさがす, 工学/情報, 工学部 |
講義投稿日:2017年8月9日 |
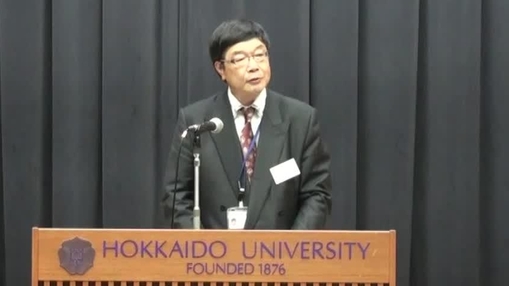
|
地域と連携したサステイナブルキャンパスの構築
|
サステナビリティ・ウィークの一環として開催されるサステイナブルキャンパス国際シンポジウムは、今回で3回目を迎えました。昨年のシンポジウムでは、キャンパスを”Living Laboratory”として活用し、大学と地域が協働した持続可能な社会を構築する重要性に関する認識が共有されました。今回は「地域と連携したサステイナブルキャンパスの構築」をテーマに、日欧の大学からサステイナブルキャンパス構築の先進的な活動事例紹介や、今年12月に終了する本学とEUの3大学との国際交流プロジェクト”UNI-Metrics”の成果も発表します。地域や民間企業と連携したサステイナブルキャンパスの将来像と、その構築のための展望を描きます。
サステイナブルキャンパス国際シンポジウム2013(オフィシャルサイト)
13:00-13:15 開会挨拶
三上 隆(北海道大学理事・副学長)
来賓挨拶
都外川 一幸(文部科学省)
13:15-13:30 趣旨説明
小篠 隆生(北海道大学大学院工学研究院)
13:30-15:05 講演―地域と大学との協働プログラムの紹介
・UDCK as a Collaboration Hub for Sustainable Urban Design
出口 敦 (東京大学)
・North West Cambridge
Heather Topel (University of Cambridge)
・社会に開かれた個性輝く大学キャンパス形成
都外川 一幸(文部科学省)
15:20-16:35 講演―UNI-Metrics”の成果と今後
・サステナビリティに関する大学評価指標の適用:北大とトリノ工科大の場合↓藤井 賢彦(北海道大学大学院地球環境科学研究院)
・Knowledge
Place and Economy: Smart Specialization and the Triple Helix framework in Amsterdam and Sapporo
Joao Romao (VU University Amsterdam)
・University Campus Energy Management: the POLITO case study and the UNI-metrics indicators application
Giulia Sonneti (Polytechnic of Turin)
16:35-17:55 パネルディスカッション(1/4)
パネルディスカッション(2/4)
パネルディスカッション(3/4)
パネルディスカッション(4/4)
パネリスト:講演者、佐藤 博(札幌市)
コーディネーター:小篠 隆生(北海道大学大学院工学研究院)
17:55-18:00 閉会挨拶 [3:59]
横山 隆(北海道大学サステイナブルキャンパス推進本部)”
|
教員:
三上 隆 (北海道大学理事・副学長)、横山 隆(北海道大学サステイナブルキャンパス推進本部) |
開講年:
|
タグ:
japanese, サステイナビリティ学教育研究センター, サステナビリティ・ウィーク, 複合分野/学際 |
講義投稿日:2017年8月9日 |

|
日本の社会変動と宗教変容
|
社会構造と社会的機能、社会変動の理論的関連をおさえたうえで、日本社会と宗教制度・教団の関係を歴史的に近年の動向もふまえつつ考察する。とりわけ、現代におけるカルト問題の構成を事例に、日本社会における社会秩序の問題を検討する。
|
教員:
櫻井 義秀(北海道大学大学院文学研究科) |
開講年:2005
|
タグ:
japanese, 学部でさがす, 心理/社会学, 文学/思想/言語, 文学部 |
講義投稿日:2017年8月9日 |

|
|
人工知能技術に基づく知的ソフトウェアの構成要素を学ぶ.この分野の技術は多岐にわたっているが,本講義では概念が記号化された以降の高次レベルでの推 論や学習および不確実性の数理的な扱いを中心に学ぶ.(それに対して,信号として与えられる低次レベルのパターンを知的に扱う技術は別の講義でなされている.)
さらに,人間の知能に加えて感覚や運動の特性まで考慮したヒューマンインタフェースのデザインの基礎を学ぶ.
|
教員:
栗原 正仁(情報科学研究科)、野中 秀俊(情報科学研究科) |
開講年:2005
|
タグ:
japanese, 学部でさがす, 工学/情報, 工学部 |
講義投稿日:2017年8月9日 |

|
貧困・民族・生活の社会学
|
なぜ発展途上国の人々は貧しいのだろうか? そもそも貧困ってなんだろう? なぜ民族紛争は起こっているのだろうか? そもそも民族ってなんだろう? 発展途上国の人びとの生活と私たちはどうつながっているんだろうか? この講義では、南北問題とは何か、貧困とは何か、発展とは何か、民族とは何か、といった問題を、なるべく具体的な“人々の生活”のレベルから考えます。
1. モノから考える南北問題
2. 「貧困」って何だ?
3. 「民族」って何だ?
4. 「村の生活」を考える
|
教員:
宮内 泰介(文学研究科) |
開講年:2005
|
タグ:
japanese, 学部でさがす, 心理/社会学, 文学部 |
講義投稿日:2017年8月9日 |

|
|
昆虫は形や行動の多様性の宝庫である。これまでに命名された真核生物の半数以上を昆虫が占めるが、その種多様性の解明度は10分の1程度とも見積もられており、われわれが目にしたことも無い未知の形を備えた昆虫がまだ沢山いることも間違いない。昆虫分類学者はその多様性の発掘に力を注ぎ、また系統学者・形態学者は、ミメティクスネタの宝庫とも言える多様性を、工学者とは違う観点で見つめている。昆虫の未知の多様性がごく最近明かされた例として、雄で交尾器が逆転した昆虫について、そして形態・系統学的観点からの昆虫の形の研究例として、昆虫の跳躍行動の進化について紹介する。
|
教員:
吉澤 和徳(北海道大学大学院農学研究院) |
開講年:2014
|
タグ:
japanese, バイオミメティクス市民セミナー, 公開講座でさがす, 北海道大学公開講座, 学部横断型プログラム, 理学部, 総合博物館, 複合分野/学際, 農学, 農学部 |
講義投稿日:2017年8月9日 |

|
|
前提科目としての経済政策論、国際公共政策学、根幹科目としての国際政治経済、ミクロ経済、マクロ経済、金融政策を踏まえた公共経営コースならびに国際政策コースにおける展開科目として1年次に開講される。グローバル化の中での国際経済関係の構造と動態を広く国際貿易、国際要素移動、国際マクロ経済にわたって理解させ、国際社会の枢要を占めるわが国における公共政策と対外経済政策のあり方、現代の国際経済社会の安定と成長に妥当なレジーム・制度と政策のあり方を考察する基礎を与える。
|
教員:
佐々木 隆生(公共政策大学院) |
開講年:2005
|
タグ:
japanese, ビジネス/経済, 公共政策大学院/公共政策学教育部/公共政策学連携研究部, 大学院でさがす, 経済学部 |
講義投稿日:2017年8月9日 |

|
|
トポロジーの基本的な考え方や歴史的発展,理工学への様々な応用をやさしく紹介する.
|
教員:
石川 剛郎(北海道大学大学院理学研究科) |
開講年:2005
|
タグ:
japanese, 全学教育科目, 学部でさがす, 理学/自然科学, 理学部 |
講義投稿日:2017年8月9日 |

|
|
1630 年、フランスの法律家 Pierre de Fermat は本の欄外に次のような内容の書き込みを残した.
「3 以上の整数に対して、不定方程式 x^n + y^n = z^n は整数解を持たない. このことの驚くべき証明を私は見つけたが、これを記すには余白が小さすぎる…」
この命題の正否はなんと約 370 年後、1995 年になるまで決着がつかなかった. 授業ではこのような問題が産まれる背景を古代の数論から掘りおこし、問題解決のためにどのような努力が払われたかを歴史を追って見ることにする. 必要な予備知識としては高校数学 I、IIA、IIB で十分である.
|
教員:
松下 大介(北海道大学大学院理学研究科) |
開講年:2005
|
タグ:
japanese, 全学教育科目, 学部でさがす, 理学/自然科学, 理学部 |
講義投稿日:2017年8月9日 |

|
|
自然とはなんだろう? 自然保護、と言うけれど、自然を守るとはどういうことだろうか? よく考えると実はそれほど簡単ではない。自然保護とは人間の手が加わらないことか? 自然保護という思想は、世界共通のものになりうるのか? それとも、文化や歴史によって違うのか?
この講義では、自然環境について、あるいは環境問題について、あくまで〈地域〉の視点、地域住民の視点を重視しながら考える、ということをやってみたいと思います。そこでは、地域の住民自身がその環境と歴史的にどうかかわってきたか、今後どうかかわるべきか、といった点が中心的なテーマになります。それは単に人が自然にどうかかわるか、ということにとどまらず、人と人の間にどういう関係を作っていったらいいのかという問題である、といったことについても考えます。講義では、こうしたことを、日本・東南アジア・太平洋地域の具体的事例を取り上げながら考えたいと思います。
さらに、この講義では、以上のような “環境と地域社会”というテーマに沿って、論文(レポート)を書いてもらいます。レポートを書くときには、何をどう調べればよいのか、どうまとめればいいのか、などについて、実践的に学びます。
|
教員:
宮内 泰介(文学研究科) |
開講年:2005
|
タグ:
japanese, 全学教育科目, 学部でさがす, 心理/社会学, 文学/思想/言語, 文学部 |
講義投稿日:2017年8月9日 |

|
|
今から約3億6000万年前のデボン紀に、暖かい沼地の浅瀬から勇気ある両生類の先祖(ユーステノプテロン)が陸を目指した。それは、水圏からの脱出、すなわち体重を支えるための骨格の劇的な進化と、空気中の酸素を獲得するための未完成な肺の誕生を生み出した。この陸上への進出がなければ、私たちヒトは今日存在しなかったのである。
本講座は、現存する両生類の中で特異的に進化した無尾目を、形態や生態、繁殖戦略や鳴き声といった生物学的側面と、絵本や物語また食文化といった文化的側面から分析し、激変する両生類周辺の環境を通して、総合的に両生類を捉えようとするものである。また文系理系を問わず、授業を通して将来研究者として必要な問題解決の視点と手法をマスターしようというものである。
|
教員:
鈴木 誠(高等教育機能開発総合センター) |
開講年:2004
|
タグ:
japanese, 全学教育科目, 学部横断型プログラム, 理学/自然科学, 理学部 |
講義投稿日:2017年8月9日 |

|
写像空間のトポロジーと幾何と特異点
|
「写像空間のトポロジーと幾何と特異点」について講義する. 幾何学や大域解析の諸問題は,多様体と多様体間の可微分写像の言葉で記述される.その際の常套手段として,扱うクラスの写像の全体に位相や微分構造を入れて,その写像空間を解析することにより,もともとの問題にアプローチするという方法がある.この方法を説明する.
その過程で,関連する幾何学の問題,大域解析の問題,さらに特異点論との関係を論じる.
幾何学や大域解析,非線形問題,特異点論に興味を持つ人に最適である.
「美しいものは皆,写像空間の特異点である」
|
教員:
石川 剛郎(北海道大学大学院理学研究科) |
開講年:2004
|
タグ:
japanese, 学部でさがす, 理学/自然科学, 理学部 |
講義投稿日:2017年8月9日 |

|
質的社会調査の方法と実際
|
社会学における分析とは何か。とりわけ質的分析に関わる研究法について考える。
社会学の学部段階における卒業論文では、殆どが質的調査を行う。しかしながら、突撃調査の域を出ていないものが多い。社会調査実習においては量的調査の分析法を習得するわけであるが、質的調査の授業科目はない。そこで、この授業科目において質的調査の基本的理解を目指す。
|
教員:
櫻井 義秀(北海道大学大学院文学研究科) |
開講年:2004
|
タグ:
japanese, 学部でさがす, 心理/社会学, 文学/思想/言語, 文学部 |
講義投稿日:2017年8月9日 |

|
グローバル・エコノミーの政治経済学
|
1990年代から形成されてきたグローバル・エコノミーを分析し,現代資本主義の構造と変動を明らかにするとともに,そこから生じた緊張や矛盾への適切な処方箋を展望する.
|
教員:
佐々木 隆生(公共政策大学院) |
開講年:2004
|
タグ:
japanese, ビジネス/経済, 学部でさがす, 経済学部 |
講義投稿日:2017年8月9日 |

|
-ありのままの自分を見つめて-
|
1. 心の発達過程を学習し、乳児~老年までの発達段階で乗り越えねばならない課題を理解する。
2. 心の深層を学習し、無意識の世界を理解する。
3. 対人場面における人間の行動について学習し、集団の影響力を理解する。
4. カウンセリングを学習し、会話を通して心の成長を促す技法を理解する。
|
教員:
和田 博美(北海道大学大学院文学研究科) |
開講年:2004
|
タグ:
japanese, 全学教育科目, 心理/社会学, 教育/学習, 文学部, 薬学研究院 |
講義投稿日:2017年8月9日 |

|
政治経済学的アプローチ
|
1.戦争と平和の原因を、国家を主体とする国際関係の構造と変動から考察し、平和の実現と維持をリアルに追求する社会科学的な考え方への案内を行う。
2.国際関係の特質をめぐる主な立場である(1)ホッブズ的無政府社会、(2)自由貿易平和主義的調和社会、(3)グロチウス的秩序社会の3者の対立と関係を理解することと、国際関係の中での政治と経済のダイナミックな関係を理解することとを通じて、国際関係をみる基本的視点を養う。
3.同時多発テロやさまざまな国際緊張、安全保障問題への日本のかかわり方を主体的に検討する知的基盤を養う。
|
教員:
佐々木 隆生(公共政策大学院) |
開講年:2004
|
タグ:
japanese, ビジネス/経済, 全学教育科目, 学部でさがす, 法律/政治, 経済学部, 複合分野/学際 |
講義投稿日:2017年8月9日 |

|
|
複雑系研究の代表的なトピックスである「カオス」「フラクタル」の基本的概念を習得します。
特に、 複雑なシステムを非線形力学系、 セル・オートマトン等で計算機上に再現し、 そこに現れる複雑な系の挙動・性質がカオスやフラクタルの概念によって特徴付けられることを、 2年次に既習の初等的なC言語プログラミングを実際に行ってもらうことで学習します。
スケジュール
(1)運動方程式とその線形化、生態系の方程式とその差分化
(2)非線形写像
(3)軌道の稠密性
(4)写像の折りたたみ度と軌道のエントロピー、軌道安定性とリアプノフ指数
(5)分岐現象とカオス
(6)数値計算の準備
(7)非線形力学系とカオス
(8)アトラクタの埋め込み次元と相関次元
(9)カオスの計算機演習
(10)自己相似性とフラクタル
(11)複素力学系と確率的フラクタル、フラクタル次元
(12)フラクタル計算機演習
(13)マルチフラクタル
|
教員:
井上 純一(北海道大学大学院情報科学研究科) |
開講年:2009
|
タグ:
japanese, 学部でさがす, 工学/情報, 工学部 |
講義投稿日:2017年8月9日 |

|
現代社会における数値計算の役割
|
現代社会においてはコンピュータの利用は必要不可欠になっている。これは単なる娯楽のためというだけでなく、高齢化社会において少ない労働力で高い作業効率を得ることが、我国の社会における課題となっているためでもある。
このことは教育現場にも当てはまり、日本全体で教材を共同で利用するなど、コンピュータやネットワークを使った教育の効率化の可能性はたいへん大きい。
このような作業効率・教育効率の向上の上では、様々な機能を提供するサーバーコンピュータ (多くは Unix ワークステーション) を使いこなせること、サーバー上でのプログラムを作成する技術、そして Webpage やプリントでの表現等の重要性が今後増していくものと考えられる。
この授業では、サーバーとして用いられている Unix コンピュータ上で実際にプログラムを組み、数値計算による問題解決を体験することを通じて、必要なコンピュータの利用法、プログラムのアルゴリズムの構築方法、計算結果の可視化 (グラフ化)、Webpage へのグラフの表示、TeX などを利用した数式・図を含むプリント作成方法等について修得することを目的とする。
|
教員:
大西 明(理学研究院) |
開講年:2003
|
タグ:
japanese, 学部でさがす, 理学/自然科学, 理学部 |
講義投稿日:2017年8月9日 |

|
日本社会の変動と家族
|
社会学固有の研究対象が「家族」であるといっても言い過ぎではない。しかし、誰もが知っており、経験もしている家族を学問の対象とすることはことのほか難しいことでもある。
近現代日本における社会変動の中で家族、家族観の移り変わりを考えたいのであるが、それには、家族を捉える様々な分析視角が必要となる。それらを簡単に解説した上で、家族の変動をみていきたい。
|
教員:
櫻井 義秀(北海道大学大学院文学研究科) |
開講年:2003
|
タグ:
japanese, 学部でさがす, 心理/社会学, 文学部 |
講義投稿日:2017年8月9日 |

|
|
確率的情報処理に関する話題の提供 : 統計力学の考え方に基づく情報処理システムの設計と その動作の解析がどのように行われるのか、を具体例をあげて解説する.
次年度は「画像/符号/スペクトル拡散通信の数理 : ベイズ統計と情報処理」、「ゲーム理論と経済現象の数理」をとりあげる予定です.
2005年度の資料も参照のこと.
|
教員:
井上 純一(情報科学研究科) |
開講年:2004
|
タグ:
japanese, 大学院でさがす, 工学/情報, 工学院/工学研究院, 情報科学研究科 |
講義投稿日:2017年8月9日 |

